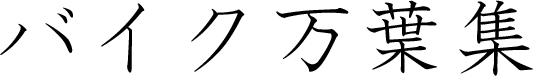「現場に下りる」トップが、企業の空気を変えた
鈴木修氏は、スズキ株式会社の元会長として知られる存在です。2024年12月に94歳で逝去するまで、現場を何より重んじる姿勢を貫き、会社の成長を支え続けました。その哲学は、いくつもの名言に表れています。ここでは、彼の言葉と、それに宿る思考の背景を辿っていきます。
現場主義を語る名言とその背景
「トップダウンというのは、トップが現場に下りることだ」
この言葉は、組織の上から命令を出すだけのやり方とは違い、トップ自らが現場の空気や課題を肌で感じながら動くべきだという考え方を示しています。鈴木氏は、現場に足を運び、ライン作業者の動きや工場の照明の数まで細かく確認していたといいます。
「メーカーは現場がどうモノを作るかが勝負で、システムや管理はあとからついてくる」
この名言も、机上の論理より現場の工夫や実践力が先だという信念に基づいています。管理や仕組みはあくまで後付けであり、実際の現場の中に答えがあるという視点が、経営判断において一貫していました。
地に足のついた経営姿勢
鈴木氏は「ケチケチ経営」とも称されるほど、無駄を嫌ったことで知られています。ただしそれは、数字だけを見る姿勢ではなく、現場を観察して本当に必要なものだけを残していく判断によるものでした。
工場では照明の明るさ、通路の広さ、作業員の動線まで見直し、生産性と効率の両立を追求。さらに営業現場でも、地域の販売店に直接出向いて酒を片手に語らう姿が知られており、組織の垣根を越えて対話する力が現場を動かしていた側面もあります。
社員の声に耳を傾け、実際に見て、話して、決める。この繰り返しが、机上の方針では得られない現実的な改善をもたらしていたと考えられます。
市場に与えたインパクト
軽自動車の強化、インド市場への進出と成功。これらはいずれも、現場から得た情報をもとに動いた結果だと言われています。スズキがインドでシェアを伸ばし続けた背景には、現地の販売動向やユーザーの声を地道に拾い上げた努力がありました。
2021年にスズキがマルチ・スズキ社を通じてインド国内で400万台超を販売したという記録にも、こうした姿勢が表れています。単なる数字の達成ではなく、地に足のついた観察と現場対応の積み重ねが、世界市場での信頼につながっていったのです。
一代でスズキを世界有数のコンパクトカーメーカーに押し上げた鈴木氏の姿勢は、いまも製造業やサービス業など、現場が力を持つ多くの業界で語り継がれています。